
友人・恩師・クラブ・キャンパスライフ…
校友だから共感できる!
そんな学生時代の思い出をのぞいてみよう。
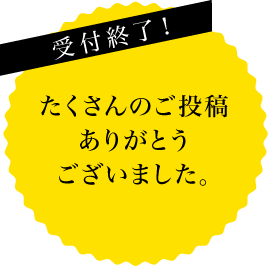


友人・恩師・クラブ・キャンパスライフ…
校友だから共感できる!
そんな学生時代の思い出をのぞいてみよう。
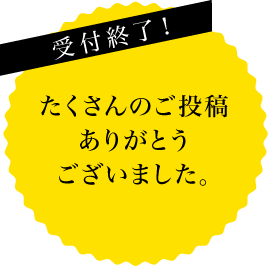
ブルックリン
家族とは一生会えないかもしれない。1950年代、アイルランドの田舎町から夢を抱いて、ニューヨークへと向かう客船にひとり乗り込む。うら若き娘エイリシュ。もちろん生まれた町から出たことがない。初めての船旅、戸惑う主人公。船酔いのため吐きそうになりながらも勇気を胸に新天地へ。やっと思いでニューヨークの港に着く。そして入国管理局の窓口でキッパリとしたとした口調で「アメリカ合衆国へようこそ」と宣言され、審査済みのスタンプがドカッと押される。ひとりドアの前に立ち、おもむろに開けると外界の光が一斉に主人公を包む。
私は、このドアを開ける瞬間を見た時、いわゆる“ルビコン河を渡った”と思った。もう後には引き戻れない。人生における決定的な場面だ。この映画『ブルックリン』は、もっとも好きな映画のひとつである。
何故だろうか、おそらく郷愁(父母がいた家庭)と哀愁(ひたる思い出)が私の胸に響くせいだと思う。そして自分の人生と重なり合う部分があるからだろう。
1974年、和歌山県の片田舎から、立命館大で学ぶために京都に移り住んだ。もちろん人生初の体験(移住)である。誰ひとり知り合いのいない大学生活が始まり、不安と共に居場所が見つからない自分を発見する。しかし時と共に、徐々に友が現れ、生活にも慣れてくる。自分の居場所も見つかり、やがて下宿先に、大学に、京都に愛着が生まれる。下宿から大学へ自転車通学。北野天満宮の前を通り抜け、一路衣笠キャンパスへ、途中豪邸が甍を並べ京都らしい町並みが広がる。忘れられない大学生活。
映画では、二つの故郷(アイルランドの田舎町とブルックリン)と愛(結婚相手)で揺れ動く葛藤が、見ているものを主人公の内面へと見事に感情移入させる。自分ではどうしようもない運命に翻弄され、些細な出来事によって決定的な人生を選択せざるをえない現実。まるで「もののあはれ」である。
本居宣長が源氏物語に見出した「もののあはれ」。文芸評論家の小林秀雄によると「もの」とは「動かし難い“もの(事実)”」で、「あはれ」とは「感情の奥底から湧き出てくる嘆き」だという。人の力では、如何とも動かし難い現実に直面して、心の深奥から嘆きを発することだろう。そしてこの嘆きを織り成し、万葉の歌が生まれ出てくる。一方、『ブルックリン』もまた、厳然と心に宿る二つの故郷、家族との別離、二つの愛に引きずられる苦悩、四季が移り変わる映像、すべて「もののあはれ」だ。
エイリシュにとって故郷アイルランドの家族は動かし難いものである。そしてブルックリンでの出来事もまた、動かし難い現実である。その狭間で揺れ動きながら、運命という名の“偶然”で人生が決まってゆく。そしてこれが私自身の人生とも重なる。
年を重ね還暦を通り過ぎると、人生の峠を越えたせいなのか、自然とノスタルジーへと向かってしまう。